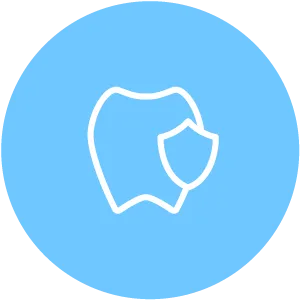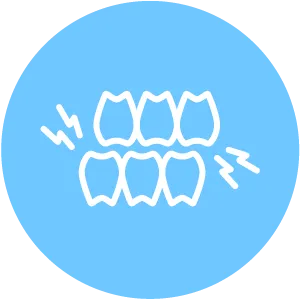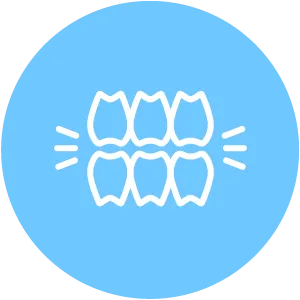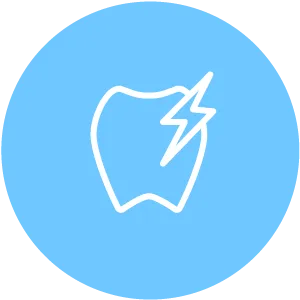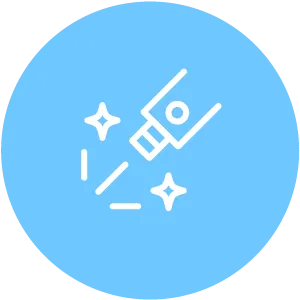親知らず
親知らずとは?

親知らず(第三大臼歯)は、一般的に18歳から25歳頃に生えてくる最も奥の歯です。現代人の顎は小さくなる傾向にあり、親知らずが正常に生えるスペースが不足していることが多く見られます。このため、様々な問題を引き起こすケースが増えています。
上下左右に1本ずつ、計4本ありますが、生まれつき親知らずがない方や、4本揃わない方も珍しくありません。
親知らずを抜歯する理由

-
1. 智歯周囲炎
(ちししゅういえん) 親知らずの周囲に細菌が繁殖し、歯茎が腫れて痛みを伴う炎症です。部分的にしか生えていない親知らずの周囲は清掃が困難で、食べかすや細菌が溜まりやすくなります。重症化すると、顔面の腫れや発熱を引き起こすこともあります。 - 2. う蝕(虫歯)の発生 清掃困難な位置にある親知らずは虫歯になりやすく、隣接する第二大臼歯にも影響を与える可能性があります。特に、親知らずと第二大臼歯の間は歯ブラシが届きにくく、虫歯のリスクが高まります。
- 3. 歯列への影響 生えるスペースが不足している親知らずは、前方の歯を押すことで歯列の乱れを引き起こすことがあります。特に矯正治療後の歯並びに悪影響を与える場合があります。
- 4. 嚢胞形成 まれに、埋伏した親知らず(完全に骨の中に埋まっている親知らず)の周囲に嚢胞(袋状の病変)が形成されることがあります。これは含歯性嚢胞と呼ばれ、顎骨を圧迫して骨を溶かす可能性があります。
抜歯の適応と判断基準
すべての親知らずを抜歯する必要はありません。正常に生えており、適切に清掃でき、咬み合わせに問題がない親知らずは保存することも可能です。
ただし、以下の条件を満たす場合は、抜歯を検討します。
反復する智歯周囲炎
親知らずの周囲に繰り返し炎症が起こり、痛みや腫れを繰り返す場合
親知らずまたは隣接歯の虫歯
親知らず自体や隣の第二大臼歯に虫歯が発生し、治療が困難な場合
歯周病の進行
親知らず周囲の歯茎や骨に歯周病が進行し、隣接する歯にも影響を与える場合
歯列への悪影響
親知らずが他の歯を押して歯並びを乱したり、矯正治療の結果に悪影響を与える場合
嚢胞の形成
埋伏した親知らずの周囲に嚢胞ができて、顎骨に悪影響を与える場合
矯正治療上の必要性
歯列矯正を行う際に、治療計画上親知らずの除去が必要と判断される場合
抜歯の手順と方法
術前検査
抜歯前には、口腔内診査とX線検査(パノラマX線写真やCT撮影)を行います。これにより、親知らずの位置、形態、周囲組織との関係を詳しく調べます。特に下顎の親知らずでは、下歯槽神経との位置関係を慎重に評価します。
抜歯の分類
抜歯の難易度は、親知らずの生え方によって異なります。
単純抜歯
完全に生えている親知らずの抜歯
複雑抜歯(外科的抜歯)
部分的に生えているか、完全に埋まっている親知らずの抜歯。複雑抜歯では、歯茎を切開し、時には骨を削除したり、歯を分割したりして取り出します。
麻酔について
通常は局所麻酔(浸潤麻酔や伝達麻酔)を行います。手術への不安が強い方には、静脈内鎮静法を併用することもあります。これにより、リラックスした状態で治療を受けることができます。
術後の経過と注意事項
正常な術後経過
抜歯後は以下のような症状が現れることがあります。
痛み
通常2-3日がピークで、1週間程度で軽減
腫れ
術後2-3日がピークで、1週間程度で改善
出血
当日はにじむ程度の出血が続くことがある
開口障害
一時的に口が開きにくくなることがある
術後の注意事項
止血
ガーゼを30分程度しっかりと咬む
冷却
術後24時間は患部を冷やす
安静
当日は激しい運動や長時間の入浴を避ける
飲食
反対側で噛み、刺激物は避ける
口腔清拭
抜歯窩は直接触らず、周囲を優しく清拭
服薬について
痛み止め(NSAIDs)や抗生物質が処方される場合があります。指示通りに服用し、アレルギーの既往がある方は事前にお申し出ください。
合併症とリスク
抜歯に伴う主な合併症には以下があります。※これらのリスクは術前の詳細な検査により最小限に抑えることができます。
ドライソケット(乾性抜歯窩)
抜歯窩の血餅が脱落し、骨が露出する状態です。強い痛みを伴い、治癒が遅れます。喫煙や過度のうがいが原因となることがあります。
神経損傷
下顎の親知らずの抜歯では、下歯槽神経や舌神経を損傷するリスクがあります。これにより、下唇や舌の感覚麻痺が生じることがありますが、多くは一時的です。
上顎洞への穿孔
上顎の親知らずの抜歯では、まれに上顎洞(副鼻腔の一つ)に穿孔することがあります。
親知らず抜歯に関するまとめ

親知らずの抜歯は、適切な診断のもとで行えば安全な処置です。しかし、すべての親知らずを抜く必要はありません。定期的な歯科検診を受け、専門医による適切な判断を仰ぐことが大切です。
不安や疑問がございましたら、遠慮なくご相談ください。患者様一人ひとりの状況に応じて、最適な治療計画をご提案いたします。早期の相談により、より良い結果を得ることができますので、気になる症状がある方は早めの受診をお勧めします。