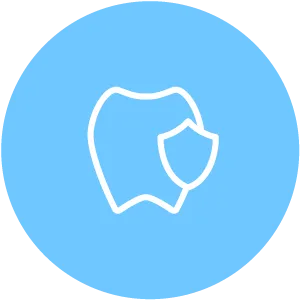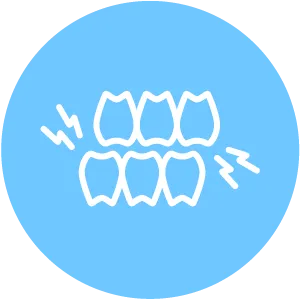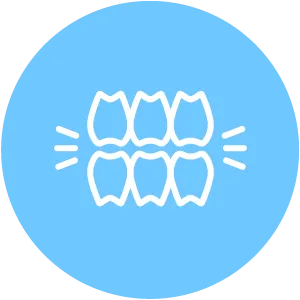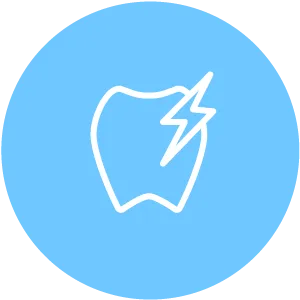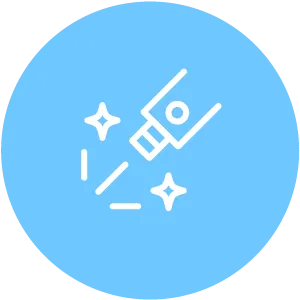顎関節症
顎関節症とは何か

顎関節症(がくかんせつしょう)は、口を開け閉めする際に重要な役割を果たす顎関節(TMJ:Temporomandibular Joint)やその周辺の筋肉に問題が生じる疾患の総称です。この関節は耳の前方に位置し、下顎骨と側頭骨を結ぶ複雑な構造をしています。関節の間には関節円板という軟骨があり、これがクッションの役割を果たしながら滑らかな口の開閉を可能にしています。
現代社会では、ストレスの増加や生活習慣の変化により、顎関節症に悩む方が増えています。特に20~40代の女性に多く見られ、軽度のものを含めると日本人の約2人に1人が何らかの顎関節の症状を経験するといわれています。単なる「あごの不調」と軽視されがちですが、放置すると日常生活に大きな支障をきたす可能性があるため、正しい理解と適切な対処が重要です。
主な症状と原因
顎関節症の代表的な症状は「顎関節雑音」「開口障害」「顎関節痛」の3つです。顎関節雑音は、口を開け閉めする際に「カクカク」「ジャリジャリ」といった音が聞こえる症状で、関節円板の位置異常や関節面の変化が原因となります。開口障害は口が十分に開かなくなる症状で、正常な開口量(約40~50mm)に比べて明らかに制限される状態です。顎関節痛は関節部分やその周辺に生じる痛みで、口の開閉時や咀嚼時に強くなることが特徴です。
これらの症状の原因は多岐にわたりますが、最も多いのが「ブラキシズム」と呼ばれる歯ぎしりや食いしばりです。特に睡眠時の無意識な歯ぎしりは、顎関節に過度の負担をかけ続けます。また、ストレスによる筋肉の緊張、不適切な咀嚼習慣(片側咀嚼など)、外傷、咬み合わせの異常なども重要な要因となります。
現代人特有の要因として、デスクワークでの長時間の前傾姿勢や、スマートフォンの使用による「ストレートネック」も顎関節症のリスクを高めることが分かってきています。
診断と治療方法
顎関節症の診断は、詳細な問診と触診から始まります。開口量の測定、関節雑音の聴診、筋肉の圧痛点の確認などを行い、必要に応じてレントゲン撮影やMRI検査を実施します。特にMRI検査では関節円板の位置や形状を詳細に観察でき、正確な病態把握が可能になります。
治療は症状の程度により段階的に行われます。軽度から中等度の場合は、まず保存的治療を選択します。保存的治療は主に以下の4つのアプローチで構成されます。
生活指導では、硬い食べ物を避ける、大きく口を開けすぎない、頬杖をつかないなどの日常生活における注意点をお伝えします。
理学療法では、顎関節周囲の筋肉マッサージや開口訓練、温熱療法などにより筋肉の緊張を和らげ、関節の可動域を改善します。
アプライアンス療法(俗にいうマウスピース療法)では、個人に合わせて製作したスプリントを主に夜間装着することで、歯ぎしりや食いしばりから関節を保護し、筋肉の緊張を和らげます。
薬物療法としては、炎症を抑える非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や筋弛緩薬を使用することもあります。重症例や保存的治療で改善しない場合には、関節腔内洗浄や内視鏡手術、最終的には関節円板の整復術や人工関節置換術などの外科的治療も検討されます。ただし、外科的治療が必要なケースは全体の5%程度と比較的少なく、多くの患者様は適切な保存的治療により改善が期待できます。
よくある質問
- Q.顎関節症は自然に治りますか?
- A.軽度の場合は自然治癒する可能性もありますが、症状が続く場合は適切な治療が必要です。早期の対処により、より良い治療結果が期待できます。
- Q.マウスピースはどのくらいの期間
使用しますか? - A.個人差がありますが、通常3~6ヶ月程度の使用で効果が現れます。症状の改善に応じて使用期間を調整していきます。
- Q.顎関節症になりやすい人の特徴は
ありますか? - A.ストレスを感じやすい方、歯ぎしりをする方、硬いものをよく噛む方、姿勢が悪い方などがなりやすい傾向にあります。
- Q.日常生活で気をつけることは
ありますか? - A.硬いものを避ける、大きく口を開けすぎない、頬杖をつかない、ストレス管理を心がけるなどが効果的です。
- Q.治療費はどのくらいかかりますか?
- A.保険適用の治療が中心となるため、初診から診断・治療まで数千円~数万円程度です。詳細は診察時にご説明いたします。