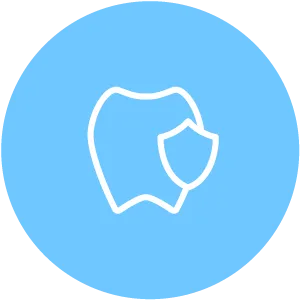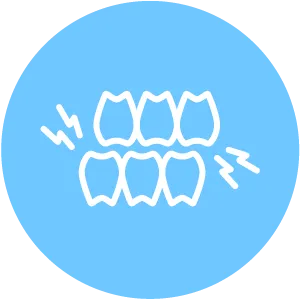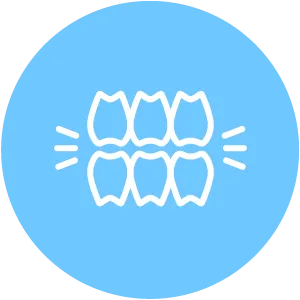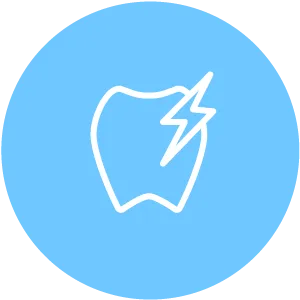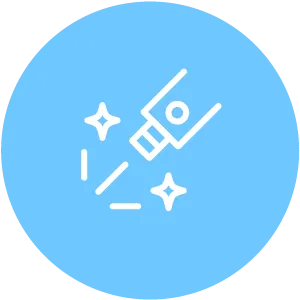この時期は乳歯の萌出が始まり、口腔衛生習慣の基礎を築く重要な時期です。生後6ヶ月頃から下顎中切歯が萌出し始め、2歳頃までに20本の乳歯が揃います。
萌出直後の歯は歯質が未熟で酸に対する抵抗性が低いため、特に注意深いケアが必要です。また、この時期に虫歯菌(ミュータンス連鎖球菌)の感染が起こりやすく、「感染の窓」と呼ばれる19~31ヶ月の時期は特に重要です。保護者からの垂直感染を防ぐため、食器の共有を避け、保護者自身の口腔衛生管理も大切になります。
歯磨きは、最初はガーゼで拭き取ることから始め、徐々に小さな歯ブラシに慣れさせていきます。この時期のフッ化物応用として、500ppm程度の低濃度フッ化物配合歯磨剤の使用が推奨されています。