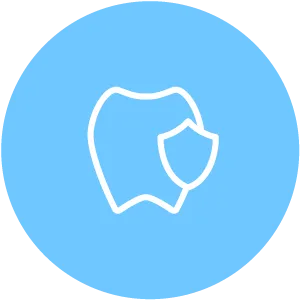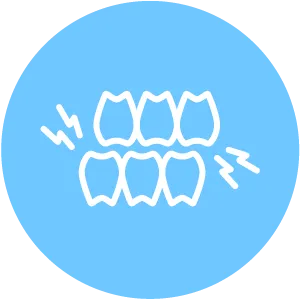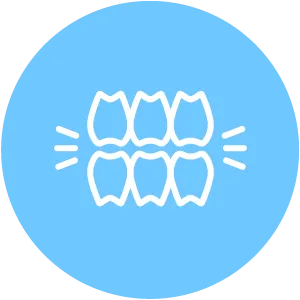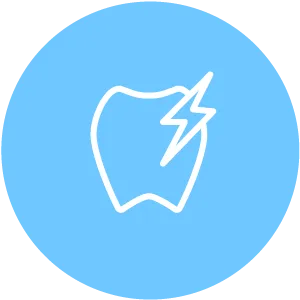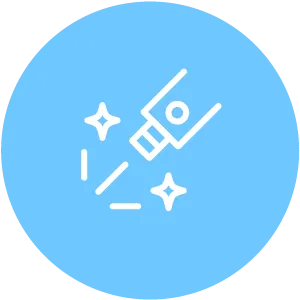知覚過敏
なぜ歯がしみるのか?
~知覚過敏のメカニズム~

「冷たいものを飲むとキーンとしみる」「歯ブラシが当たると痛い」といった症状でお悩みではありませんか?これらの症状は「知覚過敏症」と呼ばれ、多くの方が経験する歯のトラブルです。
歯がしみる仕組みを理解するために、まず歯の構造についてご説明します。歯の表面は「エナメル質」という非常に硬い組織で覆われており、その内側には「象牙質」という組織があります。象牙質には「象牙細管」と呼ばれる無数の微細な管が走っており、これらの管は歯の中心にある「歯髄(神経)」へとつながっています。
正常な状態では、エナメル質や歯肉によって象牙質が保護されているため、外部からの刺激が直接神経に伝わることはありません。しかし、何らかの原因でエナメル質が薄くなったり、歯肉が下がって歯の根の部分(象牙質)が露出したりすると、冷たいものや熱いもの、甘いもの、酸っぱいものなどの刺激が象牙細管を通って直接神経に伝わり、「しみる」という痛みを感じるのです。この現象を「象牙質知覚過敏症」と呼んでいます。
知覚過敏の原因と対策
知覚過敏の原因は大きく分けて以下のようなものがあります。
歯肉退縮による根面露出が最も多い原因の一つです。加齢や歯周病、不適切な歯磨き方法(力の入れすぎや硬すぎる歯ブラシの使用)により歯肉が下がると、本来歯肉に覆われていた歯根部分の象牙質が露出します。歯根の象牙質は歯冠部のエナメル質に比べて薄く、刺激に対してより敏感です。
エナメル質の摩耗や酸蝕も重要な原因です。歯ぎしりや食いしばり、硬いものを頻繁に噛む習慣、酸性の飲食物(柑橘類、炭酸飲料、ワインなど)の過剰摂取により、エナメル質が徐々に失われ、下層の象牙質が露出することがあります。特に現代では、健康志向から酢やレモン水を日常的に摂取する方が増えており、これらによる酸蝕症も見られます。
対策としては、まず適切な歯磨き方法の習得が重要です。軟らかめの歯ブラシを使用し、力を入れすぎないよう注意しましょう。知覚過敏用の歯磨き粉には、神経の興奮を抑える硝酸カリウムや象牙細管を封鎖するフッ化物が配合されており、継続使用により症状の改善が期待できます。また、食生活の見直しも大切で、酸性の飲食物を摂取した直後の歯磨きは避け、30分程度時間をおいてから行うことをお勧めします。
歯科医院での治療法
セルフケアで改善しない場合は、歯科医院での専門的な治療が必要です。知覚過敏抑制剤の塗布では、フッ化物や硝酸銀、シュウ酸鉄などの薬剤を患部に塗布し、象牙細管を封鎖することで症状を軽減します。これらの治療は痛みがなく、短時間で完了します。
より進行した場合には、コンポジットレジン充填や歯肉移植術などの外科的処置が必要になることもあります。また、歯ぎしりが原因の場合はナイトガード(マウスピース)の装着により、歯への過度な負担を軽減します。
重要なのは、知覚過敏の症状があっても放置せず、早期に歯科医院で相談することです。適切な診断と治療により、多くの場合で症状の改善が可能です。
よくある質問
- Q.知覚過敏は自然に治りますか?
- A.軽度の場合は適切なケアにより改善することもありますが、原因を除去しない限り症状が持続したり悪化したりする可能性があります。早期の歯科受診をお勧めします。
- Q.知覚過敏用の歯磨き粉はどのくらい
使い続ければ効果が出ますか? - A.一般的に2~4週間程度の継続使用で効果を実感される方が多いですが、個人差があります。使用方法や製品選択について歯科医師にご相談ください。
- Q.冷たいものがしみるのは
虫歯ではないのですか? - A.虫歯でも同様の症状が出ることがあります。知覚過敏と虫歯の鑑別には専門的な検査が必要ですので、症状がある場合は歯科医院で詳しく診てもらいましょう。
- Q.知覚過敏を予防する方法は
ありますか? - A.適切な歯磨き方法の実践、フッ素配合歯磨き粉の使用、酸性飲食物の摂取制限、歯ぎしり対策などが予防に効果的です。定期的な歯科検診も重要です。